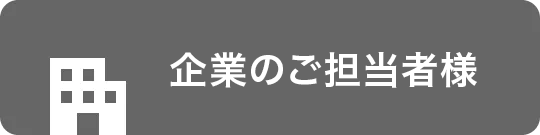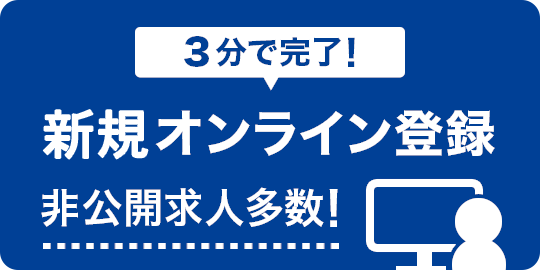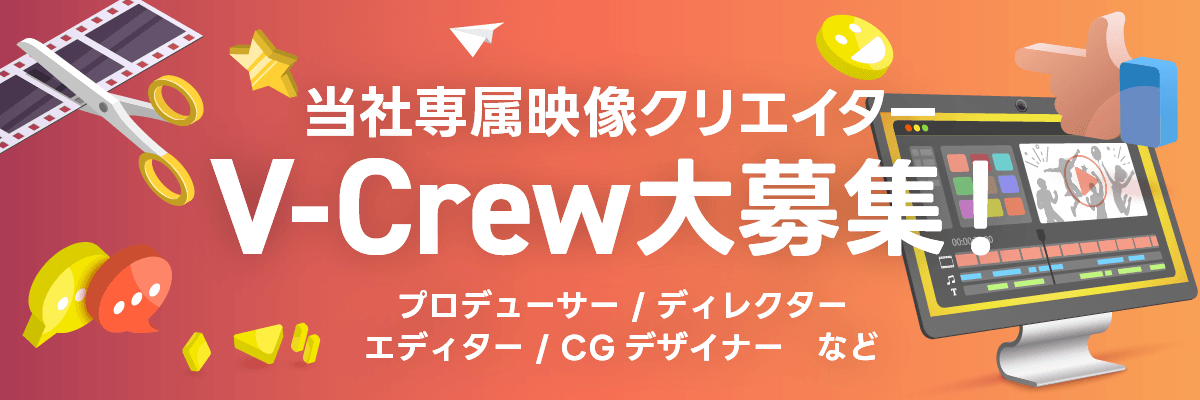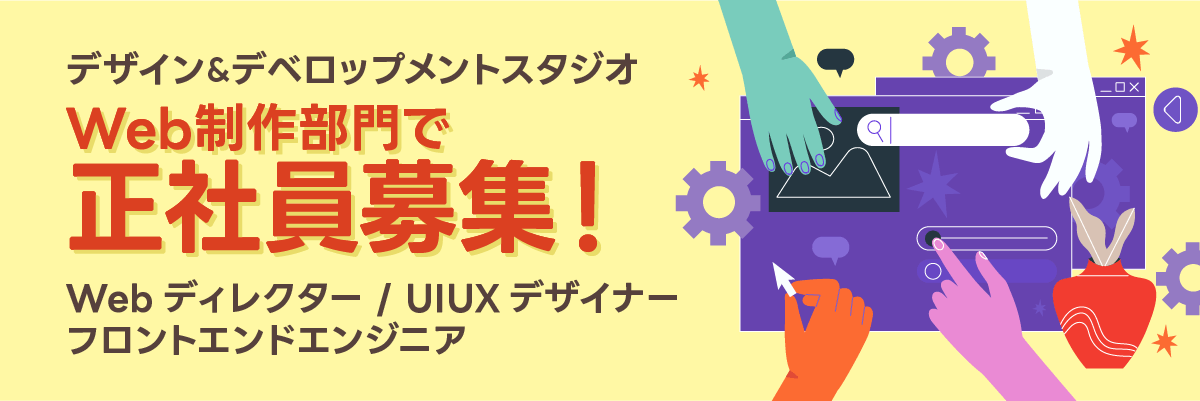観客を魅了するeスポーツの新たな映像演出方法 ~前編~
映像
観客を魅了するeスポーツの新たな映像演出方法 ~前編~

近頃、認識度が高まりつつあるeスポーツですが観戦されたことはあるでしょうか?
大規模な大会になると目を見張るような映像演出のクオリティで会場を大きく盛り上げています。その映像演出に一役買っているのが、フォトロン社が販売している映像システム「Vizrt Viz Engine / Viz Artist」。今回は「Vizrt」の技術開発を担当する山畑氏に、eスポーツイベントでの演出方法について伺いました。

株式会社フォトロン 山畑裕嗣氏
【Vizrt Viz Engine / Artist】のテクニカル担当。
学生時CG、実験映像、ビデオ/メディアアートを学ぶ。
岐阜IAMAS在学中にCGプロダクションの(株)リンクスに入社(現IMAGICA)。
ゲーム3DCGIやVFXでのCGシステムを担当後、IMAGICAで放送用リアルタイムCGシステムのVizrt Viz Engineを手掛け、現在NHKを始め各放送局のリアルタイムCGシステムの設計構築を行う。最近では紅白や音楽ライブ、esports、ライブ配信といった分野でのAR/VRテクニカルも担当する。
演出に新しい映像/CG技術を取り入れるesportsの特徴
今回esportsにおける映像についてということですが、近頃国内でもesportsへの関心が高まっているという話を皆さんも耳にされる事かと思います。
実はこの分野、あまり一般に知られていませんが、とてもクリエイティブで新しい映像/CG技術を必要とする分野なのです。特に3DCGでのリアルタイムグラフィックスを多用する点は、他の映像分野と大きく違って特徴的です。この機会に少しesportsにおける映像や演出についてご紹介させていただきます。
まずesportsというと、皆さんどのようなイメージを思い浮かべるでしょうか?
大きな会場ステージでイベントをイメージするかもしれませんし、派手なオープニングセレモニーも有名になってきていますのでその印象も大きいかもしれません。一見ライブコンサートやスポーツ中継と共通する点も多いesportsですが、実は一般のライブイベントやスポーツと比べ、3つ要素に大きな違いが出てきます。
- ・現実には存在しない出来事(PCの中での競技)
- ・会場よりもネットでの視聴者の方が多い
- ・競技が複数展開して同時進行する
従来のライブイベントであればメインの被写体(ライブイベントのアーティストやスポーツの場合はボール、プレーヤー)が存在するため、事前に入念に打ち合わせを行い映像は被写体を中心に追いかけていく形になります。ところがesportsでは、競技はゲーム機(もしくはPC)の中で行われますので、現実のカメラでゲーム映像を追いかける事ができません。
またesportsの競技を見ているユーザーというのは、会場に来ている観客よりもネット配信を見ている視聴者の方が圧倒的に多く、ゲームタイトルによってはネット配信の視聴者が1億人近くにおよぶものも存在します。その為、
ライブ会場映像 < ライブ配信映像
という図式が成り立ちやすい傾向があります。
もちろんesports会場での映像演出に力を入れるのは当然ですが、それ以上に配信映像に対してリソースを割いていく必要性が出てきます。そして視聴者に対し、同フィールド上で複数人のプレーヤーが同時に展開していく姿を漏らさず追いかけ、それぞれのフィールドで急速展開するドラマをつぶさにとらえていくわけです。
例えば世界中で人気のesportsタイトルにPLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(通称PUBG)というゲームがありますが、このゲームでは100名前後のプレーヤーが1つの島に降り立ち、最後の1名(もしくは1チーム)になるまで戦い抜きます。この仮想のフールドで同時多発に展開するプレーヤーの様を、如何にドラマティックに抜き出して映像にするのか?従来のライブコンサートやスポーツ中継にはない新しい概念であり、ここにクリエイティブで新しい映像/CG技術を使った演出が必要とされる理由があるのです。
多様なゲームに対応できるリアルタイムCG
さて、そんな独特な性質を持ったesportsですが、もう一つ頭を悩ませる重大なポイントがあります。というのも、ゲームタイトルは無数にあり、ルールが全て違ってくるのです。当然esports映像の演出も各ゲームタイトルで大きく変わってきます。
主なesportsの種類
| FPS (First Person Shooter /ファーストパーソンシューティング) |
DOOM, Halo, CS:GO, Call of Duty, Rainbow Six, 他 |
|---|---|
| TPS (Third Person shooter /サードパーソンシューティング) |
PUBG, fortnite, Splatoon2, 他 |
| RTS (RealTime Strategy /リアルタイムストラテジー) |
StarCraft, Clash Royale, 戦国大戦 , 他 |
| MOBA (マルチプレイオンライン バトルアリーナ) |
League of Legends, Dota2, Overwatch, Wonderland Wars, #コンパス, 他 |
| Battle Royale (バトルロワイヤル) |
Apex Legends, PUBG, fortnite, 他 |
| 格闘対戦 | STREET FIGHTER, 鉄拳, GUILTY GEAR, スマブラ, 他 |
| Sports | Winning Eleven, FIFA, NBA, Rocket League, WCCF, 他 |
| Racing | グランツーリスモ, iRacing, 他 |
| CCG/TCG (Collectible Card Game /Trading Card Game) |
Hearthstone, Shadowverse, 他 |
| パズル | モンスターストライク, パズドラ, ぷよぷよ, テトリス, 他 |
これらの多種多様なゲームタイトルごとに、視聴者に対してゲーム展開をより分かりやすく解説を加え、必要に応じてプレーヤー(チーム)の順位や位置、成績を紹介したりしつつ映像展開をしなければいけません。
従来のイベント映像の手法のようにPhotoshopで各種グラフィックスを制作し、After Effectsでいくつもの映像クリップを事前にレンダリングして用意する手法では必要なグラフィックスが多様であまりにも対応箇所が多く出てくるため、以前制作したCGリソースの流用もあまり期待できません。ましてやesportsはライブ競技なので、当日までチームのプレーヤー編成が公開されないこともありますし、どのチームが勝ち抜くか誰にも分かりません。対応するには当日、また競技中でも必要になったCG制作を行い間に合わせる必要が出てきます。esports映像の制作チームの負担を考えるだけで胃が痛くなりそうです。
esports映像演出の例
- ・イベント開始前のリザルトグラフィックス
- ・イベント、試合開始までのタイムカウントダウンCG
- ・イベントオープニング映像
- ・イベント会場でのスクリーン映像
- ・チーム及び選手紹介グラフィックス
- ・対戦表及びトーナメント表
- ・ゲーム画面における解説映像(INGAME)
- ・ゲーム終了後のWIN映像、スコア及び成績映像
- ・ゲームキャラクターグラフィックス
- ・リプレイ映像、その他多数
では実際のesportsでの映像演出はどうしているかというと、
ブロードキャストグラフィックスのワークフローを使ってesportsでの映像演出をリアルタイムCGで処理します
多くの方は、耳慣れない「ブロードキャストグラフィックス」という言葉に「なにそれ?」と疑問を持たれるかもしれません。
ブロードキャストグラフィックスというのは、毎日テレビでオンエアされている番組グラフィックスの事で、朝昼夕夜の情報番組やニュース番組、スポーツ中継やバラエティ番組等で使われるグラフィックスを指しますが、実はゲームのようにリアルタイムCGで制作されていることが多いのです。
少しesportsから話が逸れますが、放送ではVizrt社のViz Engineという放送に特化したグラフィックエンジンが多く使用されており、ゲーム製作に使用されるUnreal Engine 4やUnityといったゲームエンジンと似たようなものと思っていただいて構いません。放送用のゲームエンジン、といったころです。
よくニュース番組で見かけるタイトル文字やニュース項目などは、Photoshopで画像制作されていると思われている方が多いのですが、実際にはゲーム製作のようにCG空間上に予め必要なCGの元(テンプレート)を用意しておいて、番組中にボタン操作やマウス操作でリアルタイムにCGを変更させて表示させているのです。ちょうどAfter Effectsを3DCGソフトにしたような感じをイメージすると良いでしょうか。文字やマテリアル、テクスチャーを一瞬で変更してアニメーション再生し、映像入力をテクスチャーにしてリアルタイムにコンポジット(合成)処理する事ができる為、生放送の映像演出(ライブ進行する映像演出)には欠かせないものになります。
※クリックすると動画が始まります
では放送でなぜリアルタイムCGが欠かせないのか?ということですが、理由は簡単です。
PhotoshopやAfter Effectsといったソフトで毎日のCG画像や動画を作っていると番組に間に合わないのです。特に夕方のニュース番組では何時間にも及ぶ長丁場でいくつものニュースを扱うため、毎日数百ものCGを必要としますが、明日どんな事件が起きるか分からないので事前に用意するのはちょっと難しいと言えます。もちろん緊急ニュースや事件発生等はいつ起こるか分かりませんし、番組内容が直前に変更になることも良くあるため、柔軟に制作対応する必要が出てきます。
要するにCGを事前に用意する時間が十分に取れないので、これはもうゲームみたいにマウスやキーボード操作でCGの内容を変更できるようにしないととても間に合わない、と言う訳です。サッカーや野球といったスポーツ中継も同じく試合展開がどうなるか分からないので、このリアルタイムCGが日々使われています。
なんだかesportsのゲーム進行と似ている感じがしませんか?
残念ながら、放送でリアルタイムCGが当たり前のように使われているという事は国内では一般にほとんど知られておらず、海外では確立されているBroadcast Graphics Designer(ブロードキャストグラフィックスデザイナー)という職種も認知度が低いことで成り手が少ない為、常に新しい人材が求められています。
さて、ところがここ10年くらいでしょうか。
放送で使用されていたブロードキャストグラフィックスが、急速に進化を遂げるesportsと必然といった形で強く結びつきます。
シンガポールを拠点としてsportsを展開するGarena社の様子を少し見てみましょう。
※クリックすると動画が始まります
解説にAR(Augmented reality)を積極的に取り入れesportsの戦いをビジュアル化したり、天井と床をバーチャル化して狭いスタジオでは撮れないようなカメラワークを可能にしたりと、他分野でのストリーミング配信映像と比べてもesports分野は先進的な映像演出を取り込み、進化を加速させています。
ゲーム画面を映像として取り込み、その上にプレーヤー名やゲーム情報をリアルタイムに映像合成して配信することができる訳ですから、ゲーム初心者にも分かりやすく興味深い解説をビジュアルで補足して新規ユーザーの取込みを促進したり、目まぐるしく状況がリアルタイムに変化するゲーム画面を瞬時に情報追加して再ビジュアル化できるリアルタイムCGは、まさにesportsでの映像演出においてうってつけだったのです。
後編では、esports映像の進化についてお伝えしていきます。
次回をお楽しみに!
vizrtにご興味がある方はこちら
-
 To Creator編集部
To Creator編集部 -
Tips/ノウハウ、キャリアに関する情報/最前線で働く方へのインタビュー記事など、クリエイターの毎日に役立つコンテンツをお届けしていきます!