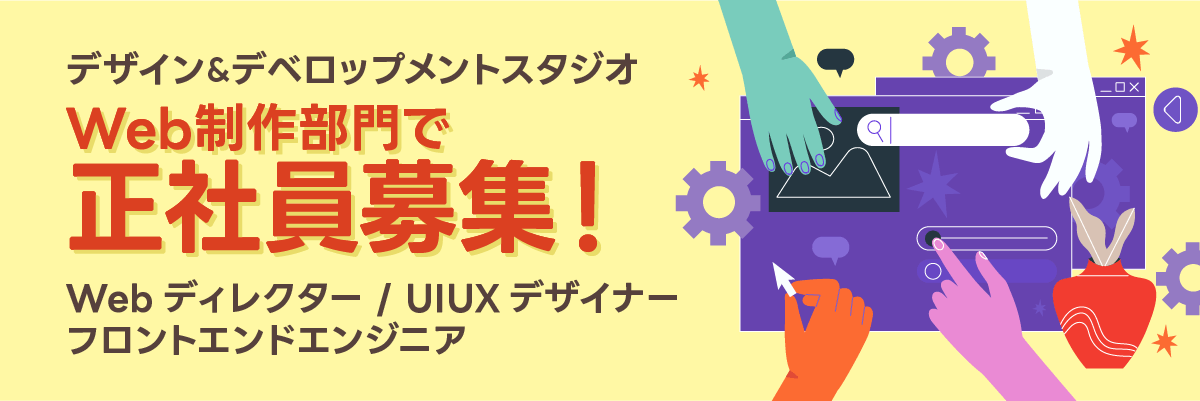アメリカからキャリアをスタート! シネマトグラファー石坂拓郎インタビュー
映像
アメリカからキャリアをスタート! シネマトグラファー石坂拓郎インタビュー

石坂拓郎:シネマトグラファー。1974年生まれ。神奈川県出身。撮影助手時代に、「セクレタリー」(02)、「ロスト・イン・トランスレーション」(03)に参加。その後、2006年にFrameworks Films Inc.を 設立する。「ホノカアボーイ」(08)には、照明監督として参加。「さくらん」(07)、「昴-スバル-」(09)、「MW-ムウ-」(09)、「ゴースト もういちど抱きしめたい」(10)、「キミとボク」(11)、「るろうに剣心」(12)、「階段のうた season6」(12/TBS)、「震える牛」(13/WOWOW)などを手掛ける。
高校時代に渡米し、大学卒業後はそのままアメリカを拠点に活動するシネマトグラファー、石坂拓郎氏。TVドラマ「ふぞろいの林檎たち」(1983年)などで知られる脚本家 / 作家の山田太一氏を父に、「101回目のプロポーズ」(1991年)や「風のガーデン」(2008年)などのTVドラマ演出家として知られる宮本理江子氏を姉に持つという映像一家で育つ。11歳離れた姉の影響が大きかったという石坂氏は、大学時代に写真にハマり、カリフォルニア州のチャップマン・ユニバーシティ・フィルムスクールの映画製作学科へ編入。チャップマンスタジオとして映画製作も行う同校の環境は、石坂氏をプロの道へと誘っていった。
ギャファー(照明チーフ)を経て、撮影監督としてキャリアをスタートさせた石坂氏は、「ロスト・イン・トランスレーション」(ソフィア・コッポラ監督|2003年)や「世界の中心で、愛をさけぶ」(行定勲監督|2003年)「拘束のドローイング9」(マシュー・バーニー監督|2005年)に撮影助手として携わり、撮影監督として「さくらん」(蜷川実花監督|2007年)、「るろうに剣心」(大友啓史監督|2012年)などを手掛け、グローバルに活躍している。そんな石坂氏の最新映画作品である、「るろうに剣心 京都大火編/伝説の最期編」の舞台裏について、そしてどのようにアメリカでキャリアをスタートさせたのかを語っていただいた!
高校から渡米し、大学では映像を志して転入!
「るろうに剣心 京都大火編/伝説の最期編」予告編
あらすじ:動乱の幕末で“最強”の伝説を残した男、緋村剣心。かつては“人斬り抜刀斎”と恐れられたが、新時代を迎えて、神谷薫ら大切な仲間たちと穏やかな日々を送っていた。そんな時、剣心は新政府から、“影の人斬り役”を務めた志々雄真実を討つように頼まれる。新政府に裏切られ焼き殺されたはずが、奇跡的に甦った志々雄は、日本政府を狙っていた。
――映像業界のご家庭に育ち、アメリカでキャリアを積まれているということですが、幼い頃から映像への道へ進もうと考えられていたんですか?
なんとなく関わりたいとは思っていたんですけど、「映像のためにアメリカに行くぞ」というほどの志ではなかったです。「とりあえずアメリカ行って、英語を覚えよう」という程度でした。
姉貴の影響が大きかったんでしょうね。僕が物心ついた時から、姉はニューヨークで暮らしていて、後に姉の友達が東京に来た時に東京案内をしてこいと、中学生の僕に言うんですよね。英語もできないのに(笑)。そういう刺激もあって、日本じゃない環境に行きたかったというのが渡米の一番のモチベーションでした。
アメリカの高校では、環境に順応することと勉強で精一杯でした。そんな中、印象に強く残っているのが、卒業生によるワークショップに参加したことです。その人は現在のノンリニア編集ソフトを作った一人で、まだWorld Wide Webも何にも無い時に、むき出しのマシンを持ってきて、AVIDの原型のようなものを見せてくれたんです。「カメラで撮って、これで編集するんだ」って。コンピューターサイエンスを学んで、映画の世界に入って、両方を融合して、こういうの作ってるって言っていたのを覚えています。
大学では、興味のあったグラフィックデザインに進み、その勉強のために写真を撮り始めました。その写真の先生がすごく面白くて、色々写真での表現する事を学びました。そして画で物語を語ることにのめり込んでいったんです。その頃から、「映像にいこうかな」って意識し始めました。
そこで、チャップマン・ユニバーシティ・フィルムスクールの映画製作学科へ編入したんです。チャップマンは急成長を遂げている学校で、今ではアメリカで最大規模の学校の一つとなり、フィルムスタジオでもあるんです。編集ルームも40部屋ぐらいあるんですよ。映画「That Things You Do!」の舞台にもなっている、カルフォルニアのオレンジカウンティにあります。
――それは刺激的な環境ですね!
プロが撮影する現場に触れられる環境でした。「演出をやりたいな」と思っていたんですが、取り敢えずフィルムプロダクション全てを一通り勉強しました。サウンド編集などを含む色々な事をやってる内に、だんだん「カメラやってよ」っていう声が増えて、気がついたらいつもカメラを担当していたんです。
運命的だったのは、チャップマンでの最後の秋、「アドベンチャー・オブ・ロッキー&ブルウィンクル」という映画作品をキャンバスで撮影をしていた時のことでした。ロバート・デ・ニーロがプロデューサーで、レネ・ルッソとジェイソン・アレクサンダーといった当時旬のキャストが出演している作品です。キャンパスはもう、毎日ものすごいフィルムセットになっていました。僕は、その照明部を手伝うチャンスを得て、撮影現場のこと、ユニオン(照明や撮影部の労働組合)のやり方を、映画「オズの魔法使い」の時から映画人の機材管理のおじいちゃんなどにバッチリ教えてもらったんです。
――そこから自然とプロの道へ繋がっていったんですか?
そうですね。その現場をやったという噂を聞きつけて、色んな人から電話がくるようになりました。学生の頃は、タダ仕事をいっぱいやりましたね。タダ仕事の方が、コネクションができるんです。有名な助監督が監督デビューのために自主制作をする。そうすると、プロとしてやってるクルーが無償で集まるわけです。そこで一生懸命やっていると「来週仕事あるんだけど来ないか?」ってなって、1日500ドルの仕事をポッてくれるんです。そうやって、より良い映画業界の人と繋がっていったんです。
――カメラマンになる前は照明としてやられていたそうですね。
最終的には、日本で言うところの技師とチーフ、アメリカだとギャファーとベストボーイと呼ばれるポジションまでやっていました。大型予算の作品では、助手としてもやってました。大きな現場に呼ばれていくと、大型照明がバーーっと並んでいて、カメラも見えないくらい遠くで作業。そして、結構暇なんです。ギャラはいいんですけれど、毎日同じだと飽きちゃって。そんな現場で一緒だったおじさんには「カメラマンになりたいなら、こんなところにいちゃいけない」って毎日のように言われるし、「じゃあ、カメアシになろう」って撮影部にいきました。しばらくは両方をやっていました。日本からのコマーシャルの仕事で操上(和美)さんの照明を手伝ったり、バイリンガルスタッフ兼カメアシで入ったりと。
――そんな人のつながりでソフィア・コッポラ監督の作品の撮影助手をすることになったんですね。
「ロスト・イン・トランスレーション」や「拘束のドローイング9」などですね。ちょうどその時、自主映画をHD24pで撮ってたんですね。HDがやっと24コマで撮れるようになった時代で、そういうHDの先駆けだったので、「24Pできるの?」って色んなところから電話かかってきましたね。
――その後、帰国され日本でお仕事をされていますが、きっかけは何だったんでしょうか?
篠田(昇)さんです。彼が岩井俊二さんと「リリイ・シュシュのすべて 」のポストプロダクションをロスにいらしていた時、パーティーでお見かけして、篠田さんの作品が好きだったので、話しかけたのがきっかけでした。
その1ヶ月後、篠田さんから「日本で一緒にやってみない?」って誘われて。で、初めて仕事で日本に行ってみたら、なんと行定勲監督による浜崎あゆみの予算3億円のMVという大きな仕事でびっくりしました(笑)。
――「るろうに剣心」も、そういう人との繋がりから関わることになったんですか?
スタッフの方から電話をもらいました。大友さんは演出家としてだけでなく、NHKであの映像をOKにさせた政治力がハンパない人だとも感じていて、周りの人に「大友監督のやり方面白いよね。いつか一緒にやってみたいな」って言っていたんです。
監督が大友さんだと聞いて嬉しくて、最初の顔合わせはSkypeだったんですが、いきなりもう、そこでワーッて色んな話になりました。僕からも精一杯アイデア出して、「オッケー、じゃあ一緒にやりましょう」となったんですね。でも、この「るろうに剣心」シリーズの制作は面白かった。美術や関わっているスタッフも、別の現場でみんな助手時代に会っていた人が多くて。それが、まさかここで、全員こういう形で集まるとは。
「るろうに剣心」始動。撮影の強力な助っ人はMoVI!

©和月伸宏/集英社 ©2014「るろうに剣心 京都大火/伝説の最期」製作委員会
――大友さんの言葉に、「アクションを撮るというのはモーションを撮るということで、でもドラマはエモーションで撮る。エモーションとモーションは一つだから、それを表現していかないといけない」とありますが、続編の「京都大火編/伝説の最期編」ではそれが大きな挑戦だったかと想像します。
第1作目の「るろうに剣心」の時からルールは同じなんです。“誤魔化しのアクション映画はダメだ”。アメリカの低予算映画のアクションシーンによくある「長玉2台で挟んで、カメラを揺らしてシャッター切って、パラパラさせて、はい、カッコいいね」ってやつ。そういうのって何が起こっているか分からないけど、凄いことやっている風に見えるんです。ごまかしのアクション撮影ですね。
でも、それを本格アクション映画で全編そうなってしまったらダメじゃないですか。だからやっぱり、「どういう意図でこの闘いのシーンが始まって、彼らは何をしようとしているのか」ってことをはっきり動線の中に入れなくちゃいけない。誤魔化さないで、ちゃんと撮る。何故ここで手が出て、どうしてここで蹴りが出るのかっていうのが、ギリギリ情報として残りながら、迫力を失わない距離感みたいなものを探さないといけない。
レンズって、被写体と離れれば離れただけ、見る人もその気分になるんですね。長玉を使ってアップで撮っていても、離れた感じになるんです。一方、ワイドレンズで近づいて撮ると、そこにいるって感じがするんです。ですから、本作はなるべく近くで撮影しています。もう、殺陣が当たらないギリギリで。これは「るろうに剣心」の時から一貫してやると決めていたことです。
――誰もが知りたいと思っていることに、あのダイナミックなアクションシーンをどうやって画に捉えたのかということです。既に情報としてCG無し、早回し無しというのは出ていますが、現場で演じているライブの迫力をどう押さえていったんですか?
本当に、(アクションに)近づいて撮ることですよね。それで殺陣が当たって、殴られてもしょうがない。シャッタースピードも、必要なところ以外は切ってないですね。ブレを無くすらために切るだけです。本当にアクションが早いんです。
――ドラマ部分とアクション部分の撮り分けは意識的にされていましたか?
やっぱり、それが一番の課題でしたね。アクションはモーション、それをどう撮り切るかの勝負。アスリートみたいなもんですよね。ところがドラマのエモーションになってくると、全く違うモードになります。あるものをありのまま撮るんじゃなくて、その後ろにある感情を撮りにいくという意識です。
撮影部がその切り替えを気持ちの部分からやらないといけないけど、そう簡単にはいかなくて。感情を撮るということでいうと、すぐに本質を見せないといった細かい所に気を配っています。格子の間から抜けて、だんだん見えてくるとか、ちょっとした工夫をしています。
アクションに関しては、本当に動きが激しいから、こっちも動いちゃうと、情報が多すぎてわけ分からなくなってしまう。だから、「るろうに剣心」では、カメラはアクションと一緒に移動するんだけど、手持ちじゃなくてレールを敷いたり、安定させたカメラの動きにしています。
続編も考え方は同じなんですが、手持ちがどうしても増えてきちゃって。理由としては、「るろうに剣心」はアクションの動線が直線だったんですが、続編では、もう、回る回る、どんどん回る。それでもなるべく安定させて撮影するために、途中からMoVIというリグを導入しました。まだ、アメリカで発表された直後だったのでプロトタイプが世界に2台しかなくて、Freefly社の社長に手紙を送ったり、最終的には現地に行ってもらって交渉して、8月にデモ機第1号を入手して、次の日から使いました。
――そのMoVIで実現出来ることは何だったんでしょうか?
ステディカムは大きいし、中間からローアングルのカメラワークが出来ないんです。MoVIは、そこが得意なんですね。それに加えて、どんなに荒れた動きをしても、手ブレしない、映像が安定する。スケジュールがとにかくタイトなのでどんどん撮らないといけないけど、時代劇だから、森、石の中庭という舞台セットに、その都度レールを敷いて、撮ってまた敷き直してなんてやっていたら、まぁ終わらないんですよ。
MoVIはレールを敷かなくてもどんどん撮れる。届いた翌日から、使い方も分からないまま取り敢えず使って、それからはほぼ毎日使いました。いやもう、たぶん無かったら出来てないです。
――MoVIを使った手持ちで様々なアングルで捉えるということは、体力的にも過酷な現場だと予想されます(笑)。
もう、相当走りましたね。役者が回る殺陣だとすると、僕らカメラマンは外周を回らなきゃいけないんです(笑)。しかもロケーションでやっているので、足場は悪い。「こっちに行ったら崖!」みたいなところで撮るんですよ。スタッフに体を抑えてもらって、落ちないようにしながら回り込んでいく。
四乃森蒼紫(伊勢谷友介)との戦いは究極に足場が悪かったですね。通りでアクションをしている役者を、僕は石垣を飛び越えて横から撮っていかなくちゃいけない。「よいしょー!」って石の上に乗って(笑)。
おまけにプロトタイプを使っていたのでMoVIも重かった。それにカメラ、サイドハンドルがついて、その中にバッテリーがあって、リモートフォーカス、ワイヤレスビデオ、自分のモニター、そのバッテリーが2個って全部付いてくと、物凄い重量になっちゃうんですよ。だから、撮影直前までスタッフにサポートしてもらうんです。瀬田宗次郎(神木隆之介)が最後の決戦で倒れて泣くシーンは、地べたから狙っていて、MoVI無しでは難しかった。 凄く可能性が広りましたね。
アクションとカメラワークの関係

©和月伸宏/集英社 ©2014「るろうに剣心 京都大火/伝説の最期」製作委員会
――アクションを先に作ってから、カメラワークを決定していくんですか?
まずは、アクション監督の谷垣(健治)さんによる予想カットを元に、ポイント、ポイントで意見を出し合って進めていきます。谷垣さんが凄くて。
例えば「ここで始まって、子供を取り返しに来ているのを回り込んで、ここでは縄を切って・・・」という風にプレゼンするんです。そのままだとワンカットで撮影するには長いので、アクションを切っていきます。一連のアイデアを監督に見てもらって、OKが出たら役者さんが場に入って、動きを監督が再度つける。でも、大友さんは、基本カットを割らないんです。とりあえず全部撮るんです。それが、物凄い大変なんです(笑)。
そして、それを見ながら台詞の位置を決めていきます。「ここだったら台詞言えますね」という風に、アクションの“間”をどこで作るか決めていく。その後、芝居から撮っていきます。斬られたり、血が出てくると一気に撮影出来ないので、その都度カットしていきます。
ただ、ワイドマスターに関しては、頭から最後まで通しでやることも多いんですよ。血がついてなくても気にしないで1回撮っちゃうんです。もしくは付いたままで。そうするとみんな、このシーンで何が起こるか、どう流れていくか把握できる。そういう流れを大友さんは大切にするのがいいんですよね。それでも、「京都大火編」の神社のシーンは、アクションあり、こっちでは刀を取りにいくわ、と大変でしたね(笑)。
カメラマンとしての挑戦

©和月伸宏/集英社 ©2014「るろうに剣心 京都大火/伝説の最期」製作委員会
――続編でも引き続き沢山の挑戦が行われたわけですが、石坂さんの中で特に大変だったことって何でしょうか?
とりあえず生き抜くことですかね(笑)。いや、本当に移動、スケジュール、ハードな撮影と大変だし、1日倒れることも許されないわけですから。
――撮影自体も、日本では初と言われているカメラマンもワイヤーで吊るされて撮った場面もあると伺っています。
しました、しました。楽しかったですけどね。僕、結構、高いところ大丈夫なので。「伝説の最期編」の後半、宗次郎が2階から飛び降りるシーンは、吊るされる以上のことをやりました。MoVIを使って、何が出来るのかって話をアクション監督のチーフの大内貴仁さんと話して出てきたのが、とにかく(役者と)一緒に飛び降りて撮りたいね、ということでした。
そういう撮り方で有名なのが、マット・デイモン主演の「ボーン・シリーズ 」なんですが、「それをどう超えるんだ」みたいな話になりました。「ボーン」はバーンって飛んだら、そこでカットなんですよね。ガシャーンって飛び込んでガラス割ってカット。それじゃあつまらないから、その後も(役者に)付いていこうって案を出しました。
可能なのかどうかわからなかったんですけど、大内さんに球を投げた。そしたら大内さんから出てきた答えは、大内さんがMoVIを持って、一緒に飛び降りるというアイデア。宗次郎役のスタントに付いてカメラを回しながら、穴に一緒に飛び降りて、着地して、そのままスタントを追い越して、回りこんで撮影をしたんです!
ジャンプの体制でアングルがズレてしまうので、そこは僕がリモートで、アングルの上下をコントロールしました。一連を20回ぐらいやって、やっと撮れた。あれは凄い大変でしたね。でも、絶対いいものになるって確信があったので、時間はかかるけどやりきりましたね。
――最後に、やりがいもあり、達成感もあった現場だったんじゃないかと思いますが、興行も大成功となりました。現在の心境をお聞かせ下さい。
やれなかったことをやれたんじゃないかな、と思ってます。一生の内に何回出来るか分からない現場の一つではあることは間違いない。スタッフみんなと話すと、「これが代表作で、あと何年僕らは代表作って言い続けなきゃいけないんだろうね」って。この作品をそれぞれがどう超えようかっていうのをもうみんな話していますね。
そういう意味で、このシリーズはいいことでもあると同時に、ずーっとこれに縛られるんだろうなとも感じていたり。ずーーっと「るろ剣みたいにしてください」と言われるのは困るでしょ(笑)。
この映画をやって、映画って共同作業だし、総合芸術だなって改めて思いました。1人の才能ではなく、みんなが持ち寄りで、凄くうまくいった。無理してでもやってやるという40代、30代、20代の、ギリギリ耐えられる体力を持ったみんなが集まった結果だったんです。罵声が飛んでもいい、意見は言うし、言われた人は結果で示す。今このタイミングで、この作品だからこそやるしかないっていうのは、みんなの共通の意識だったと感じています。
取材協力:松永勉
-
 To Creator編集部
To Creator編集部 -
Tips/ノウハウ、キャリアに関する情報/最前線で働く方へのインタビュー記事など、クリエイターの毎日に役立つコンテンツをお届けしていきます!