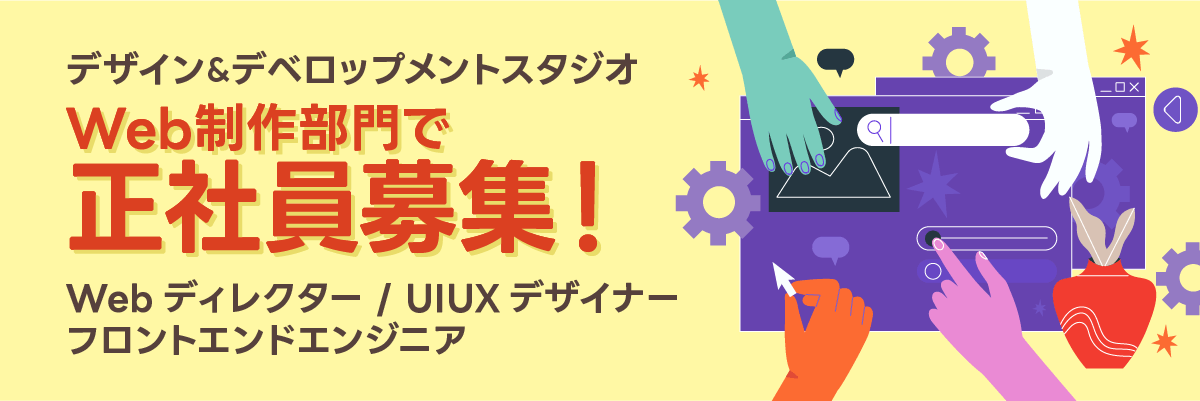今、最も求められるカメラマン内田将二。デビューから現在までの軌跡をインタビュー
共通
今、最も求められるカメラマン内田将二。デビューから現在までの軌跡をインタビュー

内田将二:カメラマン。1969年生まれ。広告、CF、ファッション、CDジャケット、PV等 撮影全般を手がける。
1999年NY-ADC賞 金賞、2002年NY-ADC賞 銀賞、1999年2000年NY-ADC賞、
2001年2003年2010年ADC賞、2012年ADC賞グランプリを受賞。
photo by 永友啓美
日本一多忙なフォトグラファーとして、日々世界中の撮影現場でファインダーを覗く内田将二氏。ミュージックビデオ(MV)では椎名林檎「いろはにほへと」、サカナクション「バッハの旋律を夜に聴いたせいです。」、 CMでは資生堂、サントリー、トヨタ自動車と、TVなどで内田氏がカメラマンを務める映像を目にしない日はないほどだ。また、フォトグラファーとしても、 多くのエポックメイキングな作品を残してきている。
今、最も求められるカメラマンの秘密を探りに、内田将二事務所を訪問した。
カメラマンになったきっかけ
――内田さんは、日本一多忙なフォトグラファー/カメラマンと聞き及んでいますが、どれくらいのペースでお仕事されているんでしょうか?
ほとんど毎日撮影しています。
――それは一日一案件撮影されているということですか?
一日の中で、撮影本番終わって、次の撮影のロケハンへ、という場合もあります。
――超人的なスケジュールとバイタリティですが、まず、内田さんが写真に興味を持ちはじめたきっかけをお伺いしたいと思います。
高校生の時、ジム・ジャームッシュの映画「ストレンジャー・ザン・パラダイス」を見て凄く印象的だったのを覚えています。映画なのに写真っぽいじゃないですか、モノクロで。それで、ああいうテイストの映像や、写真を撮ってみたいなって。映画のポスターも凄くカッコよかったんですよね。
――最初の動機は写真よりも映像だったのですね?
映像でしたね。今思えば「撮影部みんなでああいう映像を作りたい」、そういうことだったんですね。でも、最初は基本となる写真、静止したものから始めた方がいいんじゃないかなと思って、109スタジオで4年くらいスタジオマンとして働きました。僕、写真学校とか行ってないんです。だから、109に入った時は何も知らなかったんですよ。フィルムのこと、カメラのこと、シャッタースピードのことも。109で先輩に教えていただきました。
――その後24歳で独立されるわけですが、そのきっかけはどういうものだったのでしょう?
ちょうど109が出来た時に僕が入ったのですが、大きくて、凄くいいスタジオで、日々、売れっ子カメラマンがやって来るんです。そういったカメラマンの写真の撮り方やライティングを直に学べたんです。4年ほどやっているうちに、一から全て自分で手掛けたいと思って独立しました。スタジオマンの頃から、ブックを持って営業に回ったりして、雑誌や音楽の仕事が月に3、4本来るようになっていたので、やっていけるかなと思って。
――スチルから映像へキャリアの幅を広げていくきっかけは何だったのでしょう?
ミュージックビデオ(MV)が最初でした。MVが16ミリや35ミリのフィルムで撮影出来た時代、僕は27歳とかだったと思います。やっぱり、映像も面白いじゃないですか。それでいろんなMVをやるようになったんです。
一番最初に撮ったMVはSILENT POETSのジャケット撮影とのセットで頼まれたものでした。海外のロケ先でビデオを回して。面白かったな~。SILENT POETSは二人組なんですが(現在は下田法晴のソロプロジェクト)、メンバーの下田くんはアートディレクターでもあるので、別のアーティストの仕事も来るようになって。
その下田くんを紹介してくれたのが、マッキャンエリクソンの白水生路さん(a.k.a. SEIJI BIG BIRD|LITTLE TEMPOのベーシスト)という、今はマッキャンのクリエイティブの中でもベテランなんですけど、彼が美大を卒業したばかりの新卒で、歳も近いことや、二人ともダブミュージックとかレゲエ好きで九州出身というのも手伝ってロケ先で仲良くなったんです。
音楽系でいうと、映像ディレクターの牧鉄馬さんが、レコード会社でアートディレクターの頃、22、23歳の駆け出しだった僕は、ブックを見せに行ってジャケット撮影の仕事をやりはじめました。その後、TYCOON GRAPHICSと出会ってから、TOWA TEIのジャケットをやるようになりました。彼らとは凄く親しくなって、プライベートでも兄貴みたいな存在なんです。
その頃、90年代初期って、凄く面白かった時代だったんです。音楽、グラフィックス、映像って全部勢いがあって、いいカルチャーでしたよね。
ターニングポイントとなったNIKE「swim」

NIKE「swim」(2001年ADC賞)
ad: 野田凪|ca: 内田将二|cd: ジョン・C・ジェイ|cd/c: 佐藤澄子|designer: 野田凪、安藤基広|sty: 川部奈津子|hm: 鴨克也|pr: 湯川テッド勇、金 功、山本賢治、脇達也
――以降、広告へキャリアを広げられ、本当に幅広いジャンルや作風で活躍されていますが、ご自身の中でターニングポイントになった作品を教えてください。
やっぱり、NIKEの「swim」じゃないかな。アートディレクターは野田凪(1973年 - 2008年|グローバルにエポックメイキングな作品を創造してきたアートディレクター、監督)さんでした。
――衝撃的なビジュアルで凄く覚えています。
当時は、合成による表現が広告では成立していなかった頃でした。ファッションで、少しずつ出始めていた程度。ADCを受賞したのですが、ADCの歴史の中でもズバっと強いという評価を頂いています。
――どのように撮影されているんですか?
撮影は凄く大変でした。NIKEからは、リアルな方向性で一発で撮ってくれってと言われましたが、リアルとなると水着に気泡とか付いて綺麗じゃないんです。テストもしてみましたが、全然ダメで、これは合成しかないってことになったんです。
白ホリのスタジオに設置した巨大な水槽で泳いでいる人、水のテクスチャーや泡をエイト・バイ・テン(8×10)で撮影し、空は別撮りしたものを合成してい ます。何が大変かというと、水面を境に顔と体のバランスをデフォルメしているのですが、リアルさを突き詰めていくと、カッコよくならないんですよ。そのバランスがすごく難しい。リアルとファッションの狭間。これがファッション系だったら、リアルじゃなくてもカッコよければいいとなるんですが。
本当に毎日朝から晩までオペレータと一緒にMacの前に1週間くらいいました。1枚のデータ容量が重かったのもありますが、当時のMacは直ぐ止まって動かなくなる。アートディレクターが野田凪さんだから千本ノックのごとく要望がくる(笑)。頭部をどれだけ小さくすべきかのバランスが難しかった。彼女は もっと小さくしたかったんですよ、結局周りから止められましたが(笑)。
それでやっと印刷が上がって、野田さんからバイク便で送られてきて、それを見た瞬間「これはヤバい」と感動しました。頑張った甲斐があって色々賞もいただくことになりました。
――野田さんとはラフォーレ原宿の広告「ANIMAL BEHAVIOR HAIR HAT」やYUKIのMV「センチメンタルジャーニー」とエポックメイキングな作品を残されてきましたね。
彼女の作品の9割くらいはやったんじゃないかな。
――アートディレクターや監督の、ある種、型破りなアイディアや世界観を、写真や映像に焼き付けていくときに心掛けていることはあるのでしょうか?
仕事ってそれぞれにツボがあると思うんです。そのツボを押せば間違いない。ツボを分かっているかどうかで色々表現も変わってくると思うんですよね。この作品において、アートディレクターや監督がどういうもの欲しているのかというツボです。
――そのツボを外さない秘訣は何でしょう?
感覚・・・、感覚と経験じゃないでしょうか。いろんな仕事を沢山やってきましたから。それと、常にいろんなものからインスパイアを受けること。写真だけ じゃなく、洋服でも建築でも、何故これがいいか? っていうツボがありますよね。仕事も同じだと思います。この仕事は、こういう撮り方でライティングはこうして、最後にこれで定着したら絶対外さないだろうって。自分なりに今まで見てきたモノやキャリアから培われているものだと思います。
――ツボを見極める際に迷いが生じたらどうするんでしょうか? これもあるし、あれもありだな・・・という風に。
ブレないんです。現場でも全く悩みません。ライティングも、一回作ったら変えないんです。
CMのお仕事、映像のお話
資生堂 MAQuillAGE「CHU-NEW-LIP篇」
ca: 内田将二
――CMでは、自動車メーカー、化粧品メーカー、スポーツ、アパレルのCMと精力的に大量に手掛けられていますが、印象的だったお仕事はありますか?
資生堂をやった時は嬉しかった。MAQuillAGEとかビューティー系の王道ですし。それと、ビールのCMも嬉しかったですね。スタジオマンの頃に見ていたキリンラガービールの仕事も出来ました。自動車メーカーもそうですが、子供の頃に見ていたCMで自分がカメラを回すっていうのは感無量です。
――MVではどうですか?
ヴィダルサスーンのキャンペーン「FASHION×MUSIC×VS」で、Caviarの監督陣と手掛けたものでしょうか。
――Caviarの中村剛さんと田中裕介さんと児玉裕一さん(現vivision)。安室奈美恵さんとのコラボレーションで、スタイリストには「セックス・アンド・ザ・シティ」のパトリシア・フィールドが担当というゴージャスなプロジェクトでしたね。
監督、3人ともセンスが凄いですよね。その点ではやりやすかったですけど、仕事の規模的には大変でした。特に、ロサンゼルスで撮影した田中くん(70年代)は撮影が2日間しかないのに、カット数がものすごく多かった。それと、児玉くん(60年代)は、幕張メッセに5セットくらい組んで朝の6時まで撮影し ていましたね。時間が本当にないので、どんどん進めていかないといけないんです。そこが一番大変でした。これは外しそうだなとか、これはイケてないかなっていうのをピッと察知して対応しました。
――判断において瞬発力を発揮していけるのも、経験で培った壮大な脳内ライブラリからピントを素早く合わせている感覚なのでしょうか。
ええ、相当やってきたので。色んな種類やトーンがあるということが好きなんです。海外だと、車の得意な人はずっと車を撮るし、ビューティー系だとか専門が はっきりしている傾向にあるけど、僕はどんなジャンルも引き受けます。それぞれのテイスト、ツボが理解出来る。何年代の撮り方といったのも分かる。その時 その時の感覚が分かるっていうか、これはアメリカっぽいトーンで、こっちはヨーロッパのトーンでいこうと。どっちも好きなんです。
それは、日本の仕組み的に1人のカメラマンにいろんな種類の仕事を発注するからだと思うんです。この人が車を撮ったらどうなるんだろうとか、このスチールカメラマンにムービー任せたらどういう風に撮るんだろうとか。そういう考え方が日本にはあるんですね。それって面白いと思います。僕自身、いろんな内容の仕事があるから飽きないんです。だから仕事ばっかりしちゃうんですよね。
――お仕事を楽しんでいる感じが凄く伝わってきます。先ほどのような大仕事の時プレッシャーとはどう向き合ってきたのですか?
いい意味でのプレッシャーはありますが、もう散々大変な現場を経験してきているので。僕がまだ広告を始める前に、Wieden+Kennedyのキム・ヤング氏にブックを見せに行ったんです。インドで撮ったモノクロのポートレートなんですが、凄い気に入ってくれて「NIKEのランニングキャンペーンをお前がやれ」って言われました。
彼がポートランド(W+Kの本社)のJohn C Jay(ジョン・C・ジェイ|創設者ダン・ワイデンのパートナーとしてグローバルに指揮を執る)を説得してくれて、そのキャンペーンを任せてくれたんです けど、それが相当なプレッシャーで。当時、26歳くらいだったかな。その時の緊張とプレッシャーと言うと、家に帰って服を脱いだら全身蕁麻疹が出来ていた。フィルムを100本くらい回して、本当に大変な撮影だった。いつもその頃を思い出すんですよ。それに比べれば・・・とよく考えますね。おかげで今は、そんなに緊張はしないですけどね。
10年掛けて作り上げた内田組
――映像のお仕事の際には、専属のチーム内田組があると聞いています。
基本専属で、10年程ずっと同じチームで一緒です。チーフの岡部雄二が、セカンドの時から一緒にやっているんですが、チーフになってもう10年くらい経つんですけど、女房役みたいな感じ。照明は米井章文といって、巨匠石井大和さんのライトマンチーフをやっていて、僕が好きなライティングのテイストを完璧に解ってくれています。クレーンやドリーを扱う特機の谷口卓さんは、クレーンワークが本当に上手いんですよ。欲しいと思う所にズバッて(笑)。チーフの彼ら、各部署の助手を含めて総勢20名ほどのチームになります。
――内田組は現場でセッティングをはじめ、とにかく凄くスピーディーだと伺っています。
それぞれの役割分担がはっきりしているので早いんですよね。どうするのがベストか、みんな分かっているんですね。それに加え、みんな凄い性格がいいんです。喧嘩もしないし、凄く仲が良いというのも一因だと思います。そういうチームなので、現場がハードでもバッとこなせるんです。
――撮影に数ヶ月を掛けるような映画だと、例えば黒澤明監督の“黒沢組”のようによく聞きますが、CMというジャンルでもチームを作ろうと思った理由は何でしょうか?
同じ人に頼む方が色々といいなと思ったんです。チームとして出来上がるまでに時間はもちろん掛かりました。最初は狙いと違うと感じた場合、組み終わったラ イトを全部バラして、一からやり直しとかありました。でも、やっぱり、僕が想像できない光の当て方をするんですよ。そういうのを見て、僕自身勉強になったりして。そういった繰り返しを経て、今のチームが出来てきたんですね。
――人材育成も作品作りの重要なファクターなのですね。そうやって最強のチームを作り上げるとき、スキルや感覚共有のため勉強会のようなことをされているのですか?
ないですね。日頃そういった話をすることも実はないんです。やっぱり修羅場を一緒に乗り越えてきた、その蓄積ってことだと思うんです。これまでに手掛けた中でも、ヴィダルサスーンや、 資生堂のオーランド・ブルーム主演のショートフィルム仕立てのCMは、予算も規模も内容も濃いものでした。シチュエーション別でセットはいくつもあるし、演者は時間が限られている。本番前日は徹夜でライティングやカメラワークにまつわる膨大な事柄を決定していかなくちゃいけないし、そういう修羅場をみんな で乗り越えてきた結果なんですね。
パーソナルワークについて
――お仕事とは別に、ポートレートの写真集「Black Book」と、風景をとらえた「White Book」というパーソナルな作品がありますね。
「Black Book」は、26歳くらいの時にインド、その後2年くらいしてアフリカへ行って撮ったポートレートです。大きいカメラでポートレートを撮るのが凄い好きなんです。Richard Avedon(リチャード・アヴェドン)には影響されました。大きいカメラで、表情とフレーミングと光を狙ってね。ああいうポートレートって基本中の基本。モノクロでポートレートはずっと撮っていきたいなと思っているのですが、しばらく仕事ばっかりしていて作品撮りを全然していないですね。
「White Book」は、ムービーの撮影でニューメキシコ州のホワイトサンズにいった時、景色がすっごい綺麗で、撮影の合間に、制作の子のデジカメを借りて景色を撮ったものなんです。このシリーズは、(ヒロ杉山氏主催の)ZINE展にも出展しました。なかなか好評で、ちゃんとまとめて写真展をやってみようかなって思いましたね。
――それが2012年の1月にパリのT.A.Fギャラリーで開かれた個展「White Sands」ですね。
パリは大好きだし、友達の薦めもあって、小さなギャラリーで、気軽に楽しみながらやってみようかなって。ヨーロッパの人がどういう反応をするのかも知りたかったし。結果、フランス人にも好評で写真も結構売れました。
――日本でもZINE展で購入された方も多いと思います。
デジカメで撮っているから、余計な力が抜けているのがいいんでしょうね。フィルムで大きなカメラで撮る時って力が入るので、ポートレートシリーズとはアプローチがまた違う。
――ポートレートの場合はどういうところを見てシャッターを切っていくのでしょう?
本当に一瞬の仕草ですね。まず被写体をパっと見て、この人は強い写真がいいとか、動作と動作の間がいいとか、自分の中で目標を決めて撮っていると思うんです。
――いい作品に仕上げるためのポイントってなんでしょうか?
光も写真のテイストも、いろんなパターンがあると思うんですよね。僕自身の作品でも、「White Sands」「Black Book」をはじめ、ファッション・ポートレートや音楽系と、まったく写真のテイストが違いますよね。被写体を見て、光、ポージング、更にはプリントの方向性、硬くプリントするのか、ペールにソフトにするか、そういった色々な要素を自分で動かしていくことでしょうか。いろんな引き出しを揃えておくことも必要で、それはどれだけ自分がやってきたのか、撮ってきたのかじゃないですかね。撮らないと上手くならないですから、写真って。

椎名林檎の撮影を多く手掛ける内田氏。「三文ゴシップ」のワントーンの写真のアートディレクターは木村豊氏(Central67)。ライティングとアングルにこだわった作品。普段から手持ち撮影をスタイルとしている内田氏は現場でいいアングルを見つけたら、そこから細かく攻めていくそうだ。ライティングに 関しては影が出ないよう、マットな質感を狙っている。ギターもマットな質感に塗ったり、ヘアメイクもマットにと繊細に仕上げている。
内田将二の目指す映像の世界
椎名林檎「いろはにほへと」
dir: 児玉裕一|ca: 内田将二
竹林をずっと横にスクロールしていく、天気雨にあるという「狐の嫁入り」のような空気感漂うMV。監督を務める児玉裕一氏について「彼はすごい。画を見る 力もすごいんです。いい監督って画を見る力がカメラマン並みというか、下手するとカメラマンよりもあるんです」と内田氏は語る。
――本当に様々なテイストの写真、映像を手掛けていますが、内田さんの目指すフォトグラファー/カメラマンとはどういうものでしょうか?
映像の仕事も楽しいですけど、写真から始めたので、印象に残る写真をもっと撮り続けたいですね。ついこの間ロサンゼルスに行ってきたのですが、アヴェドンの「WOMAN」写真展がGAGOSIAN GALERYでやっていて、凄くいいんです。アヴェドンの壁一面のプリントを見て、もう溜息ですよ。
他にもセバスチャン・サルガド「GENESIS」の巨大写真集を目の当たりにしました。安藤忠雄デザインのブックスタンド付で、エディション500。その写真集はセバスチャン・サルガドからの地球へのラブレターなんです。本当に素晴らしく、鳥肌が立ちました。僕もちゃんとやらなきゃなって思いました。
またポートレートを撮りに、南米とかに行きたいですね。「Black Book」とはテイストを変えたものを作ってみたい。そういう時間をちゃんと作らないとダメですね。
――これから写真やムービーカメラマンを目指す人たちに、写真以外でやっておくといいことをお勧めいただけますか?
映画を観ること。映画ってやっぱり凄い。掛ける予算も凄いけど、いろんな才能や情熱が集結して作られるものじゃないですか。それを1,800円で大きなスクリーンで観られるって一番勉強になりますよ。僕は時間があったらすぐ映画館ですね。映画から光やアングルを学びます。監督を目指す人だったら演出を勉強出来ますよね、総合芸術ですから。
――最近観た映画で面白かった映画にはどんなものがありますか?
「25年目の弦楽四重奏」っていうニューヨークを舞台にした映画が良かったですよ。ヤーロン・ジルバーマンの初監督作品です。フィリップ・シーモア・ホフマンとか、クリストファー・ウォーケンといった俳優陣が渋いんです。冬のニューヨークが舞台で、アングルの切り方が上品なんです。
――映像と写真の撮影での違いってなんでしょうか?
基本、僕はないと思っています。撮っている感じは同じなんですよね。見ている光やフレーミングも同じ意識です。動いているか止まっているかの違い。ファインダーを覗いて撮っているだけですからね。
――内田さんにとって、プロとは何でしょう? これだけ求められている秘密を知りたいな、と。
なんですかね(笑)。プロって外せないですよね。
――野球に例えると、3割打率は当たり前ということでしょうか?
3割じゃだめですよ、9割はないと厳しいです。
――その9割達成を実現するには、写真やムービーの技術、知識、経験則もそうですが、チーム力も含んだ総合的なプロフェッショナルの在り方を感じました。
映像は一人じゃ何にも出来ないんです。そこが写真とは圧倒的に違う。10年以上一緒にやっているスタッフが周りにいて、初めて実現可能、その感謝は一番にあります。映像で一番大事なのはそういうとこかもしれないですね。
-
 To Creator編集部
To Creator編集部 -
Tips/ノウハウ、キャリアに関する情報/最前線で働く方へのインタビュー記事など、クリエイターの毎日に役立つコンテンツをお届けしていきます!