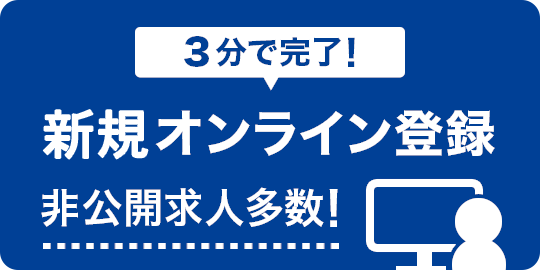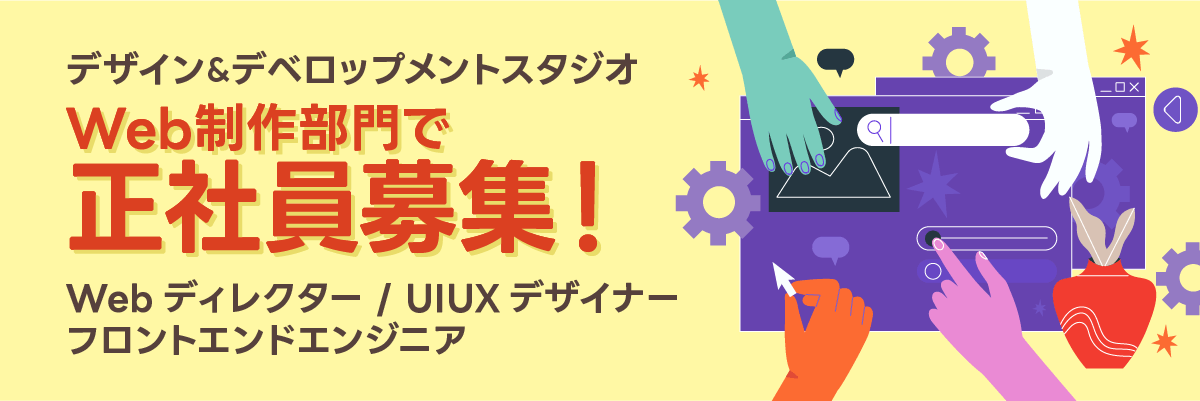「裁量ある仕事が断然おもしろい」 TVer設立メンバーの仕事観
WEB
「裁量ある仕事が断然おもしろい」 TVer設立メンバーの仕事観

「新しいことを見つけて提案し、決裁権を持って仕事を創り出すのが楽しくて、これをずっと仕事にしていきたいと思いました」
そう語るのは株式会社TVerの蜷川新治郎氏だ。日本経済新聞社のIT部門に入社した後、テレビ東京ブロードバンドに出向。そこで、主体的に働くことの楽しさを知った。その後、日本経済新聞社に戻ったものの、環境の違いに退職を決意し、転職する形で再びテレビ東京へ。そして民放5局連合のテレビ番組無料配信サービス「TVer」の立ち上げに携わる。Webという切り口で、テレビ業界の常識を変えてきた蜷川氏に、これまでのキャリアを伺った。
Webが一般に普及してすでに20年以上が経つが、未だにWeb業界のキャリアモデル、組織的な人材育成方式は確立していない。組織の枠を越えてロールモデルを発見し、人材育成の方式を学べたら、という思いから本連載の企画がスタートした。連載では、Web業界で働くさまざまな人にスポットをあて、そのキャリアや組織の人材育成について話を聞いていく。
インタビュアーは、Webデザイン黎明期から業界をよく知るIA/UXデザイナーの森田雄氏と、クリエイティブ職の人材育成に長く携わるトレーニングディレクター/キャリアカウンセラーの林真理子氏。
キャリアのスタートは、日経新聞のSE職

林: 蜷川さんは1994年に大学を卒業、就職されているんですよね?
蜷川: 大学は理工学部で、マルチメディア研究室でした。Windows95が発売される前でしたが、画像や動画に関して研究していましたね。就活は将来性を感じてシステムエンジニア職で探し、日本経済新聞社(以下、日経新聞)に1994年に入社しました。
森田: これからインターネットサービスをやっていこうという時代ですね。
蜷川: そうですね。最初に携わった仕事は、日経新聞の英字ニュースサイトの立ち上げでした。今はもうそのサイトはありませんが、「NIKKEI NET」の原型になりました。1997年頃には、経済紙のウォール・ストリート・ジャーナルがすでにデジタル版を有料化していたことから、アメリカに研究しに行ったこともありました。
林: 新聞社の社内システムではなく、キャリアのスタートからWebメディアの立ち上げに従事されたのですね。
蜷川: その後2001年から2年半、日経新聞の子会社でありテレビ東京系列の「テレビ東京ブロードバンド」(現・テレビ東京コミュニケーションズ)の立ち上げメンバーとして出向になりました。2001年は「ADSL元年」ともいわれる年。iモードが登場し、着メロを公開すると1日で50万ダウンロードされて、何千万円と売上が上がるような時代でした。テレビ東京ブロードバンドでは、任される仕事の範囲が広く、おかげで仕事観が変わりましたね。今まで仕事とは、渡されるものだと思っていましたが、新しいことを見つけて提案し、自分で創るものなんだと。提案した企画が通り、自分に任されると、裁量をもって仕事に取り組めます。この経験が楽しくて、これをずっと仕事にしていきたいと思ったんです。
刺激が少ない日々に不安が募り、退職へ
森田: テレビ東京ブロードバンドへの出向終了後は、再び日経新聞のSE職に戻ったのでしょうか?
蜷川: はい。2003年からは「NIKKEI NET」、その後、当時は「電子新聞」と呼んでいた日経電子版の立ち上げプロジェクトを担当しました。ただ、当時の日経新聞ではコンテンツづくりは記者の仕事、エンジニアはあくまで下支えする役割で、サービスやコンテンツを自ら作れる雰囲気ではなかった。テレビ東京ブロードバンドに出向していたときは、業務範囲が広く、出会いもたくさんありました。出向していた2年半で名刺を2,000枚以上も配りましたが、日経新聞に戻ってきてから名刺交換するのは社外のベンダーくらい。刺激が少ない日々に不安を覚えていきました。

林: そのことは当時、上司の方に上申や相談をされたのですか?
蜷川: 面談では「テレビ東京に戻してほしい」と言い続けていました。あるいは「エンジニアリングのスキルをベースにサービスを作る仕事がしたい」と。今でこそ日経新聞は、先進的なサービスでエンジニアが活躍していますが、当時は裏方的な役割が中心でした。結局、異動願いも新しいサービス作りも、どちらの要望も叶うことなく4年が経ち、日経電子版の開発が本格化した2008年に退職したんです。なにか道が開けるかなと思って、何も考えずに会社を辞めてしまいました。
森田: その後、テレビ東京に転職されたんですね。
蜷川: 在職中、上司からは「子会社への転職は業界のルール違反」と言われていました。しかし幸運にも、当時のテレビ東京の社長や、役員が元日経新聞の方にもかかわらず、「もう辞めているんだから問題ないだろう」と骨を折ってくれました。おかげで、契約社員としてテレビ東京に入社できました。ただいざ入社してみると、テレビ東京は中途採用をほとんどやっていなかったうえに、制作や営業の現場は人手不足。現場にとってITはそれほど重視されていなかった時代でもあって、風当たりが強かったですね。とはいえ、そんな入社経緯で自分にはもう「不退転の決意」みたいな、いい意味でがけっぷち感があったので、逆境に立ち向かっていけました。
他局がやらないWeb施策にチャレンジ
森田: テレビ東京では、どんな仕事をしていたのでしょうか?
蜷川: 配属部署は「デジタル事業推進局」で、データ放送と、ホームページやiモードなどのWebを管轄する2つの役割を担っていて、私は後者のWeb周り全般を引き受けていました。バックエンドの仕組みを考えたり、サービス編集長的な役割も、両方手がけていました。また当時は、広報媒体としての役割しかなかったホームページに、バナーを出稿できる広告枠を作り、収益化も始めました。
林: それはもう、ご自身の判断でぐいぐい進めていけたのですか?
蜷川: まるごと任されていました。並行してiPhoneアプリを作ることもありました。2010年代に入ると、オンデマンドの有料動画配信サービス「テレビ東京ビジネスオンデマンド(現・テレ東BIZ)」を始めます。この頃にはYouTubeもあり、さまざまな動画配信サービスが出てきましたね。やりたいことはたくさんありましたが、ITに膨大な投資ができる雰囲気ではなかったですし、売上も放送に比べたら、ほんのわずかな程度。利益を出して会社に貢献するというよりも、出てくる情報をキャッチアップして、ノウハウを蓄積しておき、必要なときに社内で具現化できる態勢をとっておくことに責任感を持っていました。
林: みずから新しいことを見つけて提案し、仕事を創り出すポジションを実現していかれたのですね。いろんな技術・サービスが続々と出てくる中、予算の範囲で何を試行し、何はやらないという取捨選択は、どんなふうに判断していたんですか?
蜷川: お金儲けよりも、自分たちのコンテンツが大切にされるかどうか、そして放送ビジネスにはない価値を生み出せるかどうかを意識していましたね。だから他局がやらないことに先陣を切っていました。たとえばWebでドラマのアナザーストーリーや、未公開映像を出す。他にも、テレビ朝日系の「Abema」にコンテンツを配信したり、「Netflix」「Amazon」にも出したりと、自社のプラットフォームにこだわりませんでした。1人でも多くの人にコンテンツに触れてもらうのがテレビ局の使命です。映像コンテンツを視聴する方法が増えた今、コンテンツをどれだけ流通させ、ビジネスにつなげるかが肝だと思っています。

森田: 外部のプラットフォームにコンテンツを出すことに、反対する人はいなかったのでしょうか?
蜷川: もちろん反対されました。ひと昔前は、番組をDVD化しようとすると「視聴率が下がる」と反対されたものです。みんなで同じ方向に動くためには、フラッグシップが必要です。普通は「トライアルは小さい番組から」となりがちですが、インパクトのある成功体験でないと社内の理解が得られません。『モヤモヤさまぁ~ず』『ゴッドタン』などの人気バラエティ番組がDVD化されて、結果ものすごく売れ、視聴率が下がるどころか、番組の熱狂的なファンを増やしていきました。そうすると、他の人たちも「自分の番組でもやりたい」と言い始めます。Webでは、ドラマ『勇者ヨシヒコ』の新シリーズ開始前に、過去の放送をYouTubeで一挙公開しました。「なぜ無料で見せるのか!?」と批判されましたが、「ハマる人が増えれば新シリーズを見る人が増えて視聴率が上がるし、DVDも売れる」と説得しました。2週間の限定公開で許可が下り、どのエピソードも数百万回ずつ再生され、関連売上も伸びました。その後は新シリーズが始まる度に、一挙配信するのが当たり前になりましたね。
林: フラッグシップとして大いに効いたわけですね。YouTube一挙公開は、社内で反対にあいつつも、社内のキーマンの合意をとりつけて実施に至ったということでしょうか?
蜷川: 親会社の日経新聞で電子版が成功しているので、テレビもいずれそういう時代になると経営者はわかっています。なので、現場の人よりも経営者が後押ししてくれました。世の中が変わってきていますから、テレビ局も変化しなければ取り残されるだけです。ずっとマスコミ業界にいますが、私は記事も番組も作ったことがないですし、広告営業をしたこともありません。その分、客観的な感覚を持ちながら会社に関われているのかなと思っています。
森田: 僕はあまりテレビ番組は見ないのですが、テレビをモニターとして使い、別の配信サービスのコンテンツを見ています。だからコンテンツは、テレビだけでなくネットも入れたあらゆるチャンネルで配信してほしいですね。
蜷川: そうですよね。「テレビ離れ」と言われていますが、コネクテッドTVの普及により、テレビの前にいる時間は増えていると思います。私は「コカ・コーラ理論」と呼んでいるのですが、たとえばコカ・コーラは自販機でもスーパーでもカフェでもどこでも飲めますよね。場所によって値段は変わりますが、ユーザーは好きなところで買うことができます。もし自販機でしか販売していなかったら、ユーザーの選択肢が減り、コカ・コーラがここまで普及することはなかったかもしれません。テレビも同じで、時間・場所・デバイスを選ばずに視聴できる流通網を整備したいです。
「株式会社TVer」の素案を作成
林: 「デジタル事業推進局」で結果を残した後は、どのようなキャリアを築いてこられたのでしょうか?
蜷川: その後、かつて出向していたテレビ東京ブロードバンドが、経営的に立て直す必要に迫られました。そこでIT強化を目指して、当時の上司と一緒に企画書を書いて、社長に上申。2013年にテレビ東京コミュニケーションズとして生まれ変わり、その上司が社長、私が取締役になりました。当時は2人とも40代前半でしたから、かなり思い切った人事でしたね。
森田: 古巣へ戻ってきたみたいな感じですね。
蜷川: そうですね。テレビ東京コミュニケーションズに5年間取締役として勤務したのち、2018年からは兼務という形で、テレビ東京コミュニケーションズは非常勤扱いとなり、テレビ東京ホールディングス全体のデジタル戦略を担当しました。ただ、非常勤とはいえ、気持ち的には常勤レベルで仕事をしていたように思います。
林: TVerには、いつ頃からどういう経緯で関わることになったのでしょうか?
蜷川: TVerが動き始めたのは2014年のことです。なんとなく中心メンバーになり、2015年にサービスを開始しました。当初は運営自体を外部の会社に委託していましたが、規模が大きくなるにつれ、民放5局が主体となって運営していく流れになりました。そこで、2019年に「株式会社TVer」を立ち上げる素案を私が作成し、1年近くかけて各社の経営者・広告会社・株主などに説明し、株式会社TVerの目指すべき姿を議論していきました。2020年からはTVerが私のメイン業務になっています。
林: 素案を作成された! 蜷川さんがいらっしゃらなかったら、株式会社TVerは生まれなかったかもしれませんね。
蜷川: いや、私がいなかったほうが、もっとうまく行っていたかもしれません(笑)。当時はなぜか私が素案を書く役割だったんです。
今後も、求められる仕事をしていく
林: 部下のマネジメントや後進育成は、どのようにやってこられましたか?
蜷川: マネジメントでもフラッグシップな人を作ると、周囲も頑張るようになります。チャンスは全員に均等に渡しますが、成果は平等を目指しません。できそうな人を見つけて、その人が成長できるように促すんです。すると、不思議とその人も周囲も伸びていき、結果として、会社全体として伸びるんです。最初はやっかみもありますが、成長すれば認めざるをえません。集中的に育てた人が今、テレビ東京で活躍しているのはうれしいですね。
森田: 機会は平等にすべきですが、結果は取り組んだ人たち次第ですから、平等になるわけではないですからね。今後の、蜷川さんご自身のキャリアについてはどう描いていますか?
蜷川: 現在50歳。社長になりたいとか、起業したいとか、そういう気持ちはないんです。求められるものがあれば、そこで仕事をしていきたいです。強いて言うならラグビーが大好きで、ラグビー界に貢献したいので、お声がけをお待ちいたしております!

二人の帰り道
林: 逆境や不自由こそが、人間の創造性を引き出すところって多分にあると思っているのですが、蜷川さんの仕事ぶりを垣間見るに、まさにそういう感じだなぁと脱帽です。いつが攻めどきで、いつが守備の固めどきか、時機をとらえて冷静に立ち回る手腕も冴えわたっていて、これまでのキャリア話には冒険譚を聴いているようなドキドキ感もわきあがりました。またテレビを、今後どう生かしていくべきかに対して、信念と真摯さが力強く伝わってきました。「記事も番組も作っていない」けれど、そばで現場と直接に関わり、皆が創り出しているものの本質的な価値を見抜いて、それを冷静に今後のテクノロジー進化やマーケットの変化と照合したときに、どう発展させていくべきかを客観的に洞察して方針をコンセプト立て、内外に働きかけていく。そこにご自身の活動意義を見出しているからこそ、キャリアの轍も力強い跡が残されてきたというような、大変力強くキャリア道を伺えたように思います。
森田: 当初に目論んでいたキャリアとは少し違った方向性が、ひょんなことから発生して、かつそっちへと突き進んでいくという流れのお話を伺えました。新聞に直接まつわる技術職ではなく最初からWebメディアの立ち上げ、そして出向先でサービス開発ということで、しかし振り返ってみれば、システムエンジニアに将来性を感じたという入り口があったからこそのことでもあり、まさしく先見の明があったのだといえますね。新聞やテレビという既存メディアの制作にどっぷり浸からなかったのも、結果としてTVerのようなプラットフォームを考え出すのにちょうど良かったのでしょう。なんというか、キャリアパスというのは、始めの時点では想像だにしなかったけれども、あとで振り返ってみると成るべくして成ったというような道筋であったりもするわけで、とても面白い。とはいえまだ振り返るには全然中間地点くらいですから、今後も新しい道筋を作られていくことに期待しています。
-
 株式会社 深谷歩事務所
株式会社 深谷歩事務所
代表取締役
深谷 歩 -
ソーシャルメディアやブログを活用したコンテンツマーケティング支援として、サイト構築からコンテンツ企画、執筆・制作、広報活動サポートまで幅広く行う。Webメディア、雑誌の執筆に加え、講演活動などの情報発信を行っている。
またフェレット用品を扱うオンラインショップ「Ferretoys」も運営。